プロローグ





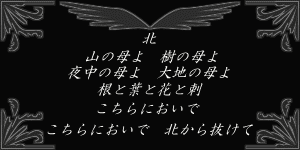

|
メチャメチャ途中です。(これで終わったら詐欺・・・)うわ〜〜やらかしてしまった。これで4thまで行かないとうそになりますよね。 enn_mama様のリクエストは秋の夜長なんですが、夜長にたどりつくのは3rdですね。これが満月だから。どうする、自分。大風呂敷を広げてしまい不安です。冬までいったらどうしよう。 でも記念すべき11111ヒットですから、ちょっとでっかい話をば・・・と思いまして。 しかし書いてしまってからなんですが、さくらちゃんはカードでこんなマシンよりもっとすごいことができるんですね〜。自分でつっこみ入れついでに、もうひとつ。秋の三日月はどんなに遅くても21時には沈みます。 この二人、そんな時間に・・・雪兎さんが必死で我慢するはずだよ。ってことはそれからも長い夜が・・・一応秋の夜長ってことで。おほほほ。 と、とりあえず頑張ります。 みあママ様 談
|