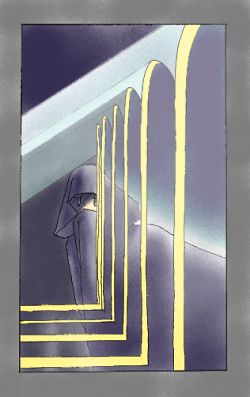
鞍の前には、ほっそりとした佳人が揺られています。鈍色の衣裾からのぞいた
華奢な足首の白さを、警備の兵は呆然として見送りました。
闇は深く、王を妨げるものはおりません。
胸元に神官様の体温を感じながら、王は考えていました。
最初は、度の過ぎた悪戯を怒っているのかと思ったのです。
手にした時間はあまりにも短く、優しい幼馴染も妙に言葉少なく。
でも。
あれは、聞き間違いだったでしょうか。
何故、彼は────。
「怖いと言ったのは───」
ふと口にしてから、思わず苦笑いをして首を振ります。いくら強い力を持つ神官とはいえ
あの狂騒の中で、見知らぬ手にさらわれて、怖くないはずがありません。
けれど、違うと思う自分が不思議でした。
神官様は、くくっと笑ってフードの陰から、澄んだ瞳でにらみました。
「王があの場で夜伽を御所望になったら、どうしようかと…」
「なんだよ、おれの事だってのか?」
「さあ」
王がむくれるうちに、愛馬は静かに足を止めました。
馬を繋ぎ、二人はそれぞれの場所へ戻らなくてはなりません。
月の入りはまだ遠く、王を見送る神官様のほっそりとした影が乾いた地面に映ります。
────わかっている。
────見ないで。
それでも物言いたげな月に背を向けて、神官様はそっと胸を押さえました。
────怖かったのは…自分だ。
王の。
固く封じたはずの心が、解けたのかと。
己の。
封が、解かれたのかと。
畏れる一方で、その時を望んでいるような。
絢爛の錦の中で、王を待つ自分が。
────怖かったんだ…。
月明かりを避け衣を目深にしたまま、神官様はすべるように歩き出し
やがて回廊の闇の中に姿を隠しました。