
チョコレートは三つ
「ひいじい様が…?」
「はい。一昨日の夜に急に具合が悪くなられて…」
深夜、大学から戻った藤隆と、その父を迎えに降りてきた桃矢はキッチンで軽い夜食を食べていた。さくらは既に部屋に引き取って眠っている。
「軽い狭心症の発作という事なので、大事はないようですが、
お年もお年なので、入院なさったようですね。」
「ふう…ん」
雑炊のレンゲを行儀悪くくわえて、桃矢は頬杖をついた。一線からは退いているものの、国内で十指に数えられる財閥の長なのだ。さぞかし大騒ぎになったことだろうと、さして同情する気もなく桃矢は考える。母の実家からは縁を切った家庭で育ち、桃矢には雨宮家に対する確たる感情があるわけでもなかった。
「さくらさん、何か変わった様子はありませんでしたか?」
「さくら?」
急に矛先を変えられて、しかし、すぐに得心がゆく。大道寺知世とさくらはお互いの母を通して遠い血縁関係にある。もしかして、知世から何か知らされていないかと、父は考えたのだろう。
「いや。何か知ってる感じはしなかったな」
「そうですか…。実はね、桃矢君。君に相談があるんです」
少しためらって、藤隆は桃矢の顔をまっすぐ見つめ切り出した。病気で弱気になったのか、曽祖父がさくらに会いたがっているというのだ。藤隆はそのことを大道寺園美に相談されたらしい。
「見舞いに行かせりゃ、いいじゃないか」
「それが、やはり、…そうも行かないらしくて…」
心なしか、歯切れが悪い。曽祖父の心の中で、藤隆あるいは木之本家に対するわだかまりは解消されつつあった。さくらが母や父、そして兄に抱くゆるぎない愛情と信頼が、頑なだった曽祖父の心も徐々に癒していた。園美が仲介役となって、名乗りこそしなかったけれど、曽祖父はさくらに会う事もしている。それまで、話さずにいた事を桃矢に打ち明けて、藤隆はふっとため息をついた。
「そこまでいってるなら…。さくらにだって、隠さなくたって…。」
「ええ。ただ、雨宮家全体の意思というのが、難しいらしくて」
「名乗るわけには、いかない?」
「…ですね」
曽祖父個人の感情はどうあれ、公的には撫子は雨宮家との一切の関係を絶ち藤隆のもとに嫁いだのだ。
ここで、まさに直系のさくら、さらに桃矢の名前が出れば、雨宮家に騒動が起るのは目に見えていた。
「僕自身も、大事な君達をそういう騒ぎには巻き込みたくありません」
「…やっかいなんだなあ、金持ちは…。それで、父さん、おれに相談って?」
こだわりのない桃矢の反応にほっとしたのか、藤隆はようやく笑い顔を見せた。
「それでね、なんとか前のように偶然を装ってお見舞いができないものか、
…策士の桃矢君なら、なにかいい知恵が出ないかと思って。」
策士は余計だと、ふくれて見せながら桃矢はくわえたレンゲを噛んで考え込んだ。父が空になった雪平をさげながら、そのレンゲをつまみ笑った。
「桃矢君。行儀が悪いですよ」
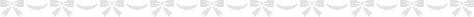
「お兄ちゃん、雪兎さんの病院って、ここ?」
友枝町から遠く離れた都心の総合病院の入り口で、さくらはぽかんと大きな口を開けて建物を見上げた。さくらでも、TVで名前を耳にした事がある。医療の質の高さもさることながら、各界のVIPクラスを顧客に迎えるサービスで有名な病院だった。エントランスホールはコロニアル風のリゾートホテルを思わせるしつらいで、スタッフのユニフォームも一見病院とは分からないほどだ。足音を吸い込む固い絨毯の廊下を歩きながら、さくらは落ちつかなげにきょろきょろと辺りを見回した。
昨日帰宅するなり、桃矢が仰天するようなニュースをさくらに持ってきた。
大学からの帰り道、雪兎が車と接触して、そのまま病院に運ばれたというのだ。幸いけがは左足の不全骨折だけで命に別状はないけれど、検査と一人暮らしの不便さを慮って少しの間入院する事になったという。
「おうちからこんなに離れた場所じゃ、かえって不便じゃないの?」
もっともな質問だった。桃矢はことさら難しい顔でうなずく。
「ぶつかってきた相手が、ぜひこの病院に…てさ。これも慰謝料のうちなんだろ。
ずいぶん金回りのいい奴みたいだったからな」
わかったようなわからぬような説明に、そんなものかとさくらはうなずく。歩くうちに、二人は病棟の入り口についた。桃矢の手荷物やさくらのリュックまで厳重なセキュリティチェックを受けて、そのあとは案内つきでようやく病棟の奥に進む。厚いオーク材のドアをノックすると、雪兎の優しい声がくぐもって返ってきた。
「さくらちゃん、わざわざこんな遠くまで来てくれたの?」
枕もとに駆け寄ったさくらの顔を見て、雪兎は申し訳なさそうにつぶやいた。きれいな空色のパジャマを着た雪兎の左ひざから下は、白いギブスに覆われていた。ギャッジベッドを調節して背中を起こし、足の下には厚いクッションが敷きこまれている。手にしていた本を脇によけて、雪兎はさくらに向き直った。
「雪兎さん、けがした所、痛くないですか? 夜眠れましたか?
お薬ちゃんと飲んでるんですか?」
矢継ぎ早の質問に一つ一つ丁寧に答えて、雪兎は微笑む。安心すると、ふいにさくらが真っ赤になって見る見るうちに瞳に涙が浮かんだ。
「よかった。雪兎さんに何かあったら、どうしようかって…」
「さくらちゃん…」
あわてた雪兎が、覗き込むようにして涙を拭う。そうしながら、さくらの背後に立つ桃矢をちらり見上げ軽く睨む。桃矢は気まずそうに咳払いをして横を向いた。
ひと通り雪兎に甘えて落ち着いたのか、さくらは物珍しそうに部屋の中を見回した。ベッドさえ、固いオーク材で仕上げられている。ここが病室であると思わせるのは目立たぬように壁に取り付けられた、酸素吸入の装置くらいだった。
「きれいな庭があるんですね」
レースのカーテンを開けると、都心とは思えぬ豊かな庭が広がっていた。病院の建物に囲まれた中庭になっているらしく、外の騒音はほとんど聞えてこない。表に面した外来病棟が明るいリゾートホテルのイメージなのとは対照的に、入院病棟はひっそりとしたイギリスのマナーハウスを思わせる。プライバシーを最優先させる患者のために、どこか隠れ家めいた雰囲気さえあった。植栽が格好の目隠しとなっているにも関わらず、庭にはほとんど患者の姿は見えなかった。
「雪兎さん、今日お兄ちゃんとお弁当を作ってきたんです。
おそとで食べませんか?
私、車椅子押しますから!」
レースのカーテンをつかんで、振り向いたさくらの瞳がきらきら輝いていた。病院の食事だけでは、とても足りなかろうと、兄と二人、あれこれと重箱に詰めて持ってきている。春らしい風呂敷に包まれた重箱をぶら下げていた桃矢が、こころなしか慌てているのを横目で眺めて、雪兎は申し訳なさそうにそうに首を傾げた。
「残念。中庭で食事をしてはいけないんだって…。
でもね、さくらちゃん。せっかくだから散歩に行こうか。
僕も、一日この部屋にいて飽きちゃったんだ」
元気に返事をしたさくらは、車椅子を調達してくると言って廊下へ飛び出していった。それを見送って桃矢は、ベッドからおりる雪兎に手を貸す。
「すまね。ゆき」
「ばれたら、僕、さくらちゃんに絶交されちゃうよ」
雪兎は上目遣いにちらりと桃矢をにらんで白い頬を膨らませた。
「だいたい、もう少しまともなプランはなかったの?
さくらちゃんに嘘をつくのも嫌だけど、本当に病気の患者さんに
申し訳なくって…。」
「…すみません」
素直に頭を下げる桃矢の前で、言い足りない文句を飲み込んで雪兎は溜息をついた。
用のないギブスは、極力軽いオープンのものだったけれど、不自由な事には変わりがない。バランスを崩さないよう雪兎を支えて、外出用の厚手のガウンを着せかける。襟を整えながら桃矢も思案気な表情で雪兎を見つめた。
「入院は、2、3日って言ってあるんだ。『退院』したら…さくらがあれこれ
世話を焼きに行かないようにしねーと…」
「大学の行き帰りにも、これ必要かな。
構内ではずしたら…みんな驚くね」
文句を言いながらも、雪兎は気楽な笑い顔で肩をすくめる。そこへ華奢な車椅子を押して、さくらが飛び込んできた。
「お兄ちゃん、松葉杖もなしで雪兎さんを立たせちゃ、
ダメじゃない!
雪兎さん、痛みませんか??」
「やかましい奴だな。ちゃんと転ばねえように、支えてるって」
言い訳する兄から奪うようにして、さくらはいそいそと雪兎の世話を始めた。暖かなひざ掛けをかけられて、ものの数分で入院患者の散歩の支度が整う。こっそり苦笑いする桃矢を従えて、さくらは車椅子を押し中庭に向かった。
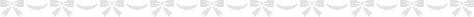
穏やかな陽射しの午後だった。
緩やかなアプローチを出て、石畳の小道をゆっくりと進む。丁寧に施行された路面は車椅子を押してもほとんど振動が伝わらない。イギリスのバックガーデンを思わせる豊かな庭だった。道は常にゆるいカーブを描き、歩く者の視線を、ある時は遮るように、ある時はひきつけるように植栽がなされている。雪兎の視線は大株の足元を細やかに飾る下植えにも注がれて、さくらに花の名前を教えながら、車椅子はなかなか進まない。桃矢は楽しげな二人の様子を眺めながら、少し遅れてのんびりとついて歩いた。
「雪兎さん、見てください」
北側の日蔭にあたる一角に差し掛かって、さくらが声をあげた。暗さを強調するように密生した高木のなかで、満開の白梅がちらちらと花びらを散らしている。その一角は日本庭園を意識したのか、小さな石の狸が下植えの陰にちんまりと置かれ、丸い頭の上に花びらを乗せていた。車椅子を止め、さくらと雪兎は花の声を聞くように、そこにじっと佇む。
「お嬢ちゃん」
ふいに、呼びかけられ振り返ったさくらが、あっと小さな声をあげた。車椅子に座って初老の男性がこちらを見つめていた。柔和な瞳と灰色の口ひげに覚えがある。
「おじいちゃん、…あの時の…」
小学生の頃、父に連れられて訪ねた別荘地で、大きな邸宅の庭に迷い込んだ事がある。その時、さくらを親切にもてなし、可愛がってくれた老人だった。先立たれた孫娘によく似ていると、笑った老人の寂しげな目を今でも覚えている。
「おじいちゃん、どこかお加減よくないんですか?」
ぺこりと頭を下げて、さくらは尋ねた。見れば付き添いの者もなく、老人は一人で車椅子に座っていた。
「なに、ちょっとここが故障しちゃってね」
老人は笑って自分の胸を指差して見せた。驚くさくらを安心させるように、定期点検なんだよと呟いて、さくらの横で頭を下げた雪兎に視線を向ける。
「さくらちゃんこそ、どうしたんだね?
こちらは、お兄さんなのかな…?」
慌てて雪兎と老人を引き合わせようとして、さくらは口ごもった。その老人の名前も知らない事を思い出したのだ。
「いえ。あの、雪兎さんはお兄ちゃんのお友だちで…。
交通事故にあっちゃって、それで…。」
しどろもどろのさくらを励まして、雪兎は微笑む。別荘地でのいきさつをさくらがようやく説明し終えた頃、軽い足音がゆっくりと近づいてきた。
「お兄ちゃん」
さくらがホッとした声をあげた。老人は、雪兎の車椅子の後ろに立った桃矢を見上げて、目をみはった。
桃矢は目顔で初対面の曽祖父に挨拶をすると、見上げる雪兎に穏やかな笑い顔を見せた。
「さくらちゃん、こちらがお兄さん?」
うなずいたさくらに紹介されて、桃矢は改めて頭を下げる。
「兄です。さくらがお世話になりました。
ありがとうございます」
「そうか。君が…」
そう言ったきり、老人は言葉に詰まる。不思議そうに振り返るさくらに桃矢は声をかけた。
「さくら。少しおじいさんと散歩したらどうだ?
ゆきは俺が連れてくから…」
「そうだね。僕は大丈夫だから。
さくらちゃん、ゆっくりお話ししてらっしゃい」
雪兎にもそう勧められて、さくらは嬉しそうにうなずいた。
二人を見送って、やれやれと桃矢は雪兎の車椅子のストッパーをはずした。
「歩いていくか? ゆき。」
「やだよ。ちゃんと看病しないと、さくらちゃんにいいつけるよ」
笑う雪兎の頭を小突いて、桃矢は来た道をゆっくり引き返した。車椅子は滑らかに石畳の上を動きアプローチを昇る。さくらが押していた時とまるで安定感が違う。雪兎はゆったりと背中を預け後ろの桃矢を振り仰いだ。
「…なんだ?」
「なんでもないよ」
「…」
心地よさそうな雪兎の表情に、桃矢の表情がふと緩んだ。
「お前宛のチョコレート、どっさり預かってるんだよな」
「チョコレート?…ああ。今日14日だったっけ」
そういえば、病院の昼食のデザートがチョコレートムースだった。この日、桃矢は煩わしい女性軍を極力避けて一日を過ごす。けれど、今日は午前中どうしても落とせない講義があった。結局、休みの雪兎の分もあずかる羽目になり、かさばる袋をさげ大学を逃げ出してきたのだ。気楽なお遊び気分のものから、本気のものまで様々に思惑が入り混じったチョコの包みを眺めて、義理堅い桃矢はどうしても憂鬱な気分になる。チョコをずらりと並べて気楽に笑う雪兎がうらやましいといえばうらやましかった。
「さくらちゃん、ちゃんと李君にチョコあげたのかな。
お見舞いなんか、よかったのに…」
「その辺は、しっかりしてるぞ。見舞いの後は
ちゃんとデートだ。あいつがここまで迎えに来るとさ」
おもしろくなさそうな顔で横を向く桃矢の顔を眺めて、雪兎は明るく笑う。
「今年もさくらちゃん、手づくりしたの?」
「ああ。昨日はそれもあって大騒ぎさ。ひいじい様宛のチョコをあずかって、
今年も園美さんが宅配係だぞ。」
そういった桃矢は、雪兎の顔を見つめたままふと考え込んだ。雪兎が小首を傾げる。
「なに?」
「…いや。くだらねえことさ。」
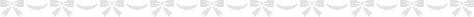
病室でコーヒーを飲みながら、取り留めのない話をするうちに、明るい声と共にさくらが戻ってきた。
「遅くなってすみません。雪兎さん」
「おかえりなさい。楽しかった?」
雪兎に水を向けられ、ベッドの傍に座り込んださくらは老人との楽しかった時間を話し出す。軽いとはいえ心臓を患っている曽祖父だ。疲れ果てただろうにと、慮りながら、桃矢は一方で思う。
天衣無縫な明るさと、年齢よりはるかに大人びた細やかさを兼ね備えて、さくらは魅力的な少女に成長している。曽祖父にとって、それは何よりの薬になるはずだった。雪兎の前で、頬を輝かせて話しつづける愛らしい妹を眺めて、桃矢は穏やかに笑った。
「そうそう。雪兎さん。お兄ちゃん。」
話に一区切りつけて、さくらはいそいそとリュックサックを膝に引き寄せた。ファスナーを大きく開け、きれいなオレンジ色と若草色の包みを取り出して、それぞれを二人に差し出す。
「僕に? ありがと、さくらちゃん」
小学生のころから恒例となっているさくらの手づくりチョコを、雪兎はかしこまって受け取る。さくらも雪兎も様々な思いを経て、二人の間柄はいつも優しい。それを証しするような、柔らかな色合いの包みを手にして雪兎は嬉しそうに笑った。
「お兄ちゃん、どうしたの?」
差し出された若草色の包みを見つめて黙っている兄に、さくらが口を尖らせた。
「大丈夫だよ。ちゃんと味見して、雪兎さんとおそろいで作ったんだから」
先手を取られて桃矢は苦笑いする。
「そうじゃねえよ。俺によこしたら、あいつの分がなくなるだろ」
「李君のこと? とーや」
「おまえの事だから、あのじいさんに1個あげちまっただろ。
おれは構わねえから、あいつにきちんと渡しておけよ」
さくらが夕べ手作りしてリュックに詰めたチョコレートは3つだった。今日、あの老人と出会って、きっとさくらはチョコレートを渡したいと考える。足りない分をどうするつもりだろうと、さっき雪兎と話しながら、ふと桃矢は考えたのだ。
相変わらず気の回る兄に、さくらが赤くなって小さな声で呟いた。
「ありがと。お兄ちゃん。
でも、小狼くんには、ちゃんとお話しするから。
小狼君ならわかってくれるよ」
ほどなく、その小狼が病室に姿をあらわした。急激に身長が伸びて、もう1年もしたら雪兎を追い越すかもしれない。雪兎を見舞う声が以前より一段低かった。
「李君。ほんとにおっきくなったね」
驚く雪兎の言葉に、赤くなって笑うと、年相応の幼い表情がたちまち戻ってくる。持ち込まれた見舞いの点心で、賑やかにお茶の時間を過ごした後、小狼は礼儀正しく挨拶してさくらを伴い病室を後にした。ふわりと静けさが戻った部屋の中で、桃矢が大きなため息をついた。
まったく文句を言う隙を与えない小狼の立ち居振舞いだった。
「やられたね、とーや」
「全くだな。」
雪兎にからかわれても桃矢は逆らわない。以前であれば、おそらく桃矢へのチョコレートが、老人に手渡されただろうと思う。その位置を小狼にとって変わられて、桃矢はおもしろくない顔で肩をすくめた。
「さくらの奴、俺がすねると思ったか?」
「そんなことないよ。さくらちゃん、言ってたでしょう?
チョコレート、僕ととーやとお揃いだって。」
「……」
ここでも1本取られた気分で、桃矢は赤くなる。雪兎に促されて包みを開けると、大きなハート型におそろいの飾り付けをしたチョコレートが顔をのぞかせた。たどたどしく書かれたメッセージを読みながら、ふいに桃矢が苦笑いする。同時に雪兎も笑い出した。
「さっき、おじいさんにあげたチョコに、李君宛のメッセージ書いてあるだろうね。
ボーイフレンドの名前、ばればれだな」
「今ごろ、思い出して噴火してるかも知れねえぞ…あいつらしいや」
ひとしきり笑って、桃矢はほっと肩の力を抜く。
「ゆき。早くよくなれよ」
「はい」
いたずらそうに肩をすくめる雪兎を、レース越しの明るい陽射しが照らすのを眺めて、桃矢も穏やかに笑った。
Fin
うううん(^_^;)今年も雪兎さんから桃矢君への
甘いチョコはなしですわ。
昨年書いたお話から、たぶん1年たっているんだと思うんですが…。
管理人は、このあたり大変大雑把に出来てますので…。
あまり追求しないでやってください(笑)
挿絵な二人は→こちら(86KB)
 TOPへ
TOPへ


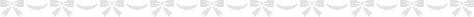
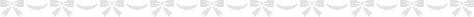
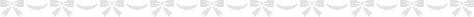
 TOPへ
TOPへ