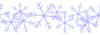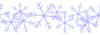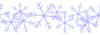水底の月
(1)
「やけに冷えてきたなあ」
「道路、滑りやすいから気をつけてね」
玄関先まで送りに出てきた雪兎が、冷気に肩をすぼめた。ここ何日か、強い寒気の影響でひどく気温が下がっている。いっそ泊まっていけば、と言いたいのを飲み込んで、雪兎は手袋をする桃矢の横顔を見つめた。それを感じたのか、桃矢が顔を上げてちらりと笑う。
「ゆっくり時間取れなくて悪いな。ちょっとバイト突っ込みすぎちまった」
「ぼくの事は心配ないから。無理しないで、ちゃんと休みを取ってよ」
このところ大学で顔を合わせる以外は、なかなかお互い時間を取れずにいる。年末のかきいれどきに、桃矢のバイトがフル回転なのはいつもの事だったけれど、今年はいつにもまして過密スケジュールの様子だった。今日も日が落ちてから、ほんの少しの時間夕食に立ち寄り、また家庭教師の仕事に出かけてゆく。
「無理はしてねーよ。俺が会いたいだけだ。」
あっさりと言ってのけて、桃矢は雪兎の肩を引き寄せ長い腕を回す。
「ゆきが、俺の顔、忘れたら困るからな」
どっちが、と憎まれ口をききかけた唇を暖かくふさがれて、雪兎は素直に目を閉じた。やがて名残惜しそうに唇が離れ、ひんやりとした頬が触れる。桃矢は雪兎を抱きしめたまま、小さくため息をついた。
「こんだけ辛抱してバイトに励んでんのにな…。肝心の誕生日は、
相変わらずファミリークリスマスか…。」
「いいじゃない。ぼくは楽しみだよ。」
そろそろ刻限だ。
辛抱、というニュアンスに思わず赤くなって雪兎は桃矢の腕を解き、背中を押す。そうして、まだぐずぐずと離れたがらない桃矢の耳元に呪文を唱える。
「じゃあさ。二次会は僕のうちで。…それでいい?」
「…」
ぱっと桃矢の耳が朱に染まった。
時々足を滑らせながら、桃矢の後姿が遠ざかってゆく。雪兎は静かに家の中に戻ると戸締りをし、外灯を消した。
ごく自然な動作が、ふと止まる。
そういえば、近頃外灯を消すことがなかった。桃矢が訪れるかもしれないと、心のどこかで思うからだろう。手に触れるスイッチを見つめたまま、少しの間考え込んでいた雪兎は、やがて自嘲気味に笑うと小声でつぶやいた。
「…うそつきだね、ぼく」

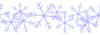
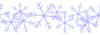

街にクリスマスが近づいていた。
商店街やそれぞれの街並み、そして雪兎が通う大学のちょっとしたコーナーにも、クリスマスらしい小物が飾られて、無彩色の季節を彩っている。
予定の講義を受けて、この後はゼミの教授のもとに行かなくてはならない。少し時間が押している。雪兎は急ぎ足でキャンバスを横切り教授の研究棟に向かっていた。
昨日からの氷雨で、石畳が濡れている。建物伝いの小道を足元を気にしながら歩き、角を曲がろうとした所で、雪兎の足が突然こわばった。激しい胸騒ぎと耳鳴り。歯車が突然大きく歪んだような、空間の不安定感。そして断層と強烈な光。思わず漏れそうになる叫び声をこらえて、雪兎は目を見開いた。
────あの人だ…。
さくらに何事か起ったのだ。光が瞬時に純白の翼に変じ視界を覆う。「何事か」がなんであれ、この瞬間、全てが雪兎の手の届かない所に委ねられようとしていた。
白い翼に身を委ね、瞳を閉じようとした雪兎は、しかし、はるか彼方、翼の向こうに垣間見える光景に息を呑んだ。
雪兎が向かおうとしていた研究棟の入り口に、自分自身が立っている。服装も持ち物も寸分たがわぬ姿で、自分が立っている。
そして、その横に桃矢がいた。
傘を差し掛けられ、ちょっと身をかがめ照れたように笑う。
「雪兎」がポケットのハンカチを取り出した。
────なぜ…?
叫ぶ声が光に飲み込まれる。
そこで、雪兎の意識が途切れた。

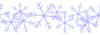

水底の月(1) 〔了〕
水底の月(2) TOP