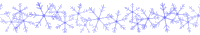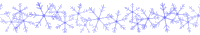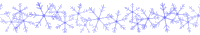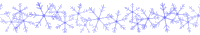ふたり
(1)
「どうも御機嫌斜めだな」
冷たい風と雪が遠慮なく入り込んでくるドアをぴしゃりと閉めて、桃矢がつぶやいた。外の氷室から、少量の野菜を運び込んで、暗くなってきた部屋の明かりをともす。台所で下ごしらえをしていた雪兎が顔を上げた。
「誰が?ぼく?」
シンクで野菜を洗いながら桃矢は笑う。
「いいな。御機嫌斜めのゆき、か。どうやってご機嫌取りしようかな」
「ばかなこと言ってないで。
それより、何?ご機嫌斜めって」
「そろそろ晴れてもいいはずなのにな。なかなか雪があがらない」
「…それ、って…」
ちらりと不安げな視線を送ってくる雪兎に、桃矢は憂鬱そうに頷いた。
「ああ。どうも『吹雪』の奴が居座っているな」

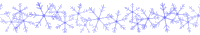

明けて早朝、迷う桃矢について、雪兎は森に入った。
「家に閉じこもったら、ますますいけないんじゃないの?」
そう笑う。森の冬空を支配する『吹雪』は、いたく雪兎を気に入っているらしい。雪兎が森で過ごすようになった最初の頃、桃矢が吹雪を避けるようにして雪兎を家に置き、それが吹雪の勘を逆なでしてしまったことがあった。(☆)
「まあな。
お前に構って欲しいんだろうが、…勘弁して欲しいぜ」
「そんな事言って、聞えたら、雪に降り込められちゃうよ」
そんな会話をしながら、二人は焚き付けに使う細い枝を拾い集めていた。
厚い雲の向こうに明るい影となって太陽が見える。どうやら空模様も小康状態で、時折吹き抜ける風が
雪華を散らす他は穏やかな朝だった。地吹雪で柔らかな雪が吹き飛ばされた斜面に、細い枝が転々と埋まっているのを、雪兎は体をかがめていねいに拾い集める。
ふと、風がやんで、伸ばした手の先に薄い影が浮かびあがった。
「結構集まったね、とーや」
顔を上げて、目の前に立った重装備の桃矢に笑いかける。気がつくと、桃矢は手ぶらだった。小枝をいったんどこかに集めたのかと、尋ねようとした雪兎を、唐突に長い腕が抱きしめた。
唐突である事には、驚かない。
けれど、自分が抱えた小枝が桃矢を傷つけるのではないかと、雪兎はうろたえ、そのはずみで小枝がばらばらと足元に散った。
唇をふさがれ、おとなしく目を閉じた雪兎の耳元を、冷たい風がかすめてひゅうと鳴った。妙に寒い。
突然、奇妙な違和感を感じて雪兎が目を開けると、桃矢は薄く笑って腕を解いた。一瞬風に巻かれて息が詰まる。再び目を開けたとき、桃矢の姿はなかった。
「ゆき?何やってんだ」
ぎょっとして飛び上がった雪兎が振り返る。
両手に小枝をいっぱいに抱えた桃矢が、沢むこうの小さな木の下に訝しげな表情を浮べて立っていた。
「そいつは…」
枝を両手に抱え、小声で話す雪兎の横顔を眺めて、桃矢はため息をついた。二人は、雪が舞い始めた固雪の道を家に向かっている。再び天候が崩れる前に家に入らなくてはならなかった。
雪兎がとっさに判別できないほど、桃矢に姿を似せて、降り立ったのは『吹雪』に間違いない。
「おまえに直接手を出しやがるなんて…あったまにくんな」
「…」
吹雪にされた事を雪兎は口にしなかったけれど、桃矢にはある程度察しがついているらしい。知らなかったとはいえ、婉曲に責められているような気がして、雪兎はしょんぼりとうつむいた。
(2)
「なんか、暖まらないな。」
「そう?暖炉の調子よくないのかな」
珍しくフリースを重ね着した桃矢を心配して、雪兎は暖炉をのぞき込んだ。上部から真っ直ぐ伸びる煙突の調子も別に異常は見当たらず、火はいつもと変わらなく燃え盛っている。
「風邪、ひいた?」
気遣わしげに雪兎がつぶやき、桃矢の額に触れた。この人外の森で桃矢が病を得たら、雪兎にはなす術がない。桃矢はその手を握って、安心させるように笑った。
「大丈夫だよ。熱がでる時の悪寒とは違うからな。単に寒いだけ。
心配するなって」
「うん。…だけど、今日は暖かくして、早く寝なよ」
まだ終わっていない家の中の仕事は自分がするから、と、雪兎はさっさと桃矢をロフトに追い上げ、パジャマを手渡した。そうは言っても、まだ宵の口だ。桃矢は苦笑いして雪兎の肩を引寄せた。
「早く寝るのもいいけどさ。」
「そういう事を言ってるんじゃないんだけどな」
「おれは、そういう事を言ってるんだ」
いうなり雪兎の体をひっさらって、ベッドに倒れこむ。桃矢の下敷きになって、雪兎は甘えた悲鳴をあげた。
「ちょっと待ってよ、とーや」
「だめ」
「お皿、洗わなくちゃ」
「放っとけよ、そんなもん」
雪兎がなだめようとするのを圧倒して、桃矢の手がもどかしげに動く。ボタンダウンや下に着たTシャツをたくし上げただけで、桃矢の手が無遠慮に侵入し始めた。
時々、こんな風にして桃矢に抱かれる事がある。それは、乱暴さを装っているけれど、充分に制御した力で戯れついているだけだ。拗ねて見せたり、甘く降参したり、雪兎の反応を一通り楽しんで、桃矢の行為は潮がひくように穏やかないつもの顔を取り戻す。ベッドに沈んで桃矢の相手をしているうちに、体の中にジワリと熱が生まれて痺れるように全身を伝っていった。小さなため息をついて、雪兎は囁いた。
「とーや…熱い…」
いつもなら、こんなひと言が合図になる。桃矢は体を起こし、するすると雪兎の服を脱がせて、もう一度ベッドにもぐりこむ────いつもなら。
しかし、桃矢は雪兎の言葉を無視してさらに体重をかけた。チノのウエストを緩めただけで、乱暴に体を押し開こうとする。雪兎が悲鳴をあげた。
「まって、…やだ、こんな…」
体に絡みついたままの洋服が、柔らかな鎖のように雪兎の自由を奪う。黒っぽい洋服から途切れ途切れに覗く素肌が、うっすらと朱に染まるのを見つめ、桃矢の目が光った。
瞳の中を粉雪が渡っていくようだ。
今朝────あの林の中で…二人いた────『桃矢』
恐怖に大きく喘ぐ雪兎を見おろして、『桃矢』は愛しそうに囁く。
「────雪兎」
息を飲み、今度こそ雪兎は必死の力で抵抗し始めた。こぶしを握り、全身をばねとして。『桃矢』は、その抵抗をいとも簡単に押さえ込み、しかし、そこで不愉快そうに眉をひそめた。なぜ、雪兎が拒絶するのか、分からない────そんな表情で。
「い…やだ…っ!!」
ぱんと大きな音が『桃矢』の頬で鳴った。
はっと息を飲んで、二人はお互いを凝視する。途端に、桃矢がかすかにうめいて体を傾かせた。
「あ…いつ……くそ…っ」
「とーや?…とーや?」
すうっと冷気が首筋に吹き付ける。雪を連れた風が吹き込み、竜巻のように二人を引き剥がした。
竜巻が雪兎をベッドに叩き込む。衝撃に一瞬ひるんだだけで、雪兎は起き上がろうともがいた。そうして桃矢を探す。
桃矢は壁際に追いやられていた。冷気の檻に封じ込められ、青ざめた表情で雪兎を見つめている。
「とーやっ!!」
雪兎がベッドを飛び出した。駈けよりざま小さな椅子の背を掴み振り上げる。桃矢の視線がぶれて、何か叫んだ。次の瞬間、雪兎は後ろから強烈な力で鷲掴みにされ、ベッドに引き戻される。転がった椅子がロフトから居間に落ちて、大きな音を立てた。
『桃矢』が仰向けに倒れこんだ雪兎の上に覆い被さった。恐ろしく冷たい。彼の周囲は空気まで凍りついて、キンと音を立てそうだった。氷の手が、悲鳴をあげる雪兎の服にかかった。
「…やだ…っ」
事態を悟った雪兎が、弱々しく首を振る。
意のままにされるのは嫌だ。絶対に。
その覚悟で抵抗しているつもりなのに、体が動かない。
『桃矢』から直接流れ込む冷気が、雪兎から抵抗する力を急速に奪っていた。『桃矢』がゆっくりとのしかかる。冷たい体を、もう押しのける力もない。
「……や…」
強張った首筋を冷たい唇でなぞられて、呼吸が詰まった。張り裂けるほどに目を見開いて、桃矢が何か叫んでいる。
………ごめん…とーや…
急速に意識が遠のいていく。白い頬を、涙が伝った。
(3)
深い海の底で、ふいに暖流に出合ったようだ。ぬくもりを探し、冷たく重い腕を伸ばして、そして目が覚めた。
火傷をしそうなほど熱い体が、雪兎を抱いていた。
けれど、まだ寒い。
吸い込む空気さえ熱く感じられて、肺が悲鳴をあげる。
「ゆき」
震える声が呼んだ。繰り返し、泣くように。
「…あ…っ」
一気に細胞が目覚めた。そうして、凍った記憶も。
恐怖と、怒り、そして絶望。見開かれた目────。
叫び声をあげそうになった時、桃矢の大きな体が雪兎を押し包んだ。
「大丈夫、俺だよ。あいつは行っちまったから」
「なぜ…あんな、ひどい…」
「俺の体を使いたかったって」
「…」
「直接抱いたりしたら、お前が死んじまう。
だから、俺の体を使いたかったって。」
「…」
桃矢の中に入り込んで、そのまま首尾よく雪兎を抱くつもりでいたのに、見破られ、激しく拒絶されてしまった。『吹雪』も引くに引けなかったのだ。
「ほんとに、死んじまうかと思った…お前、完全に冷たくなってて…」
体温を奪われ意識を失った雪兎に、うろたえた『吹雪』は、桃矢を冷気の檻から解放したのだ。暖炉の炎さえ凍てつかせる『吹雪』を追い出し、桃矢は、ひたすら雪兎を腕の中で暖めるしかなかった。朦朧とした表情で、雪兎がしがみついても、なお。
そんな言葉を切れ切れに、桃矢は雪兎を抱いた。冷たく弛緩していた全身が、自分の手に反応して震えるのが、この上なく愛しい。うっすらと汗ばむほど、丹念に手を施して、桃矢は改めて雪兎を見つめた。さっきから、雪兎は白い肌をほんのりと桜色に染めて身を捩るばかりで、目を固く閉じ、桃矢を見ようとしない。
「ごめん。怒ってるよな。
どうも、俺、あいつと波長が合うのか、掴まりやすいんだな…」
雪兎は唇をきゅっと噛んで、首を振った。
桃矢に対して怒っているのではないのだ。
もちろん『吹雪』のやり方に対して怒りはある。
けれど、それ以上に雪兎は自分に怒っていた。
抵抗し切れなかった。
よりによって桃矢の目の前で、だ。
口を開くと子どものように泣いてしまいそうだった。
その時だ。またひやりと冷気が降りてきて、雪兎ははっと目を開けた。眉をひそめた桃矢も、雪兎を体の下に抱いたまま、慎重に目を上げた。
『吹雪』は、いた。
雪兎のすぐかたわらに。
僅かに体を傾け、佇んでいる。
「来ないで」
震える声で、雪兎は言った。
けれども『吹雪』は身動きしない。じっと雪兎を見つめている。
────なんだ…?
桃矢が眉をひそめた。雪兎は目に見えて動揺していた。視線が定まらず、ふうっと目元を赤らめたかと思うと、涙のつぶが浮かぶ。
────こいつ、ゆきに何を吹き込んでやがる。
自分にそっくりの姿だけでも不愉快なのに、『吹雪』が自分を蚊帳の外に置いて、直接雪兎を口説いていると気がつき、桃矢は気色ばんだ。
「────おい」
怒りを含んだ桃矢の声に、反応したのは、意外なことに雪兎だった。身を乗り出そうとする桃矢を、引き戻し、涙をためた目で首を振る。そうなると、しつけの良い飼い犬よろしく、桃矢は口をつぐむよりない。
────泣かれると弱いのは、俺もいっしょか。
『吹雪』が礼のつもりか、冷たい手で雪兎の髪に触れた。そのまま離れ難いのだろうか、髪に触れ、頬に、そして────。
「いい加減にしやがれっ!!」
たまらず桃矢が叫んだ。

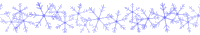

上空では、まだ風がうなっていた。けれど、不機嫌には聞えない。
不機嫌なのは今度は桃矢だった。
さっきまでの不振を取り返すように、暖炉の火が一気に燃え始め、小屋の中はみるみる室温が上がっていた。くるまっていたダウンケットをはねのけて、桃矢は汗を拭った。いきなり素肌をさらされた雪兎が、抗議の声をあげるのに構わず、さらに深く体を重ねる。シーツに沈んで、雪兎が喘いだ。
「あいつに触られて、何て声出すんだよ」
そういいながら、雪兎に言い訳する暇をあたえない。ことさら彼の弱いところばかりを責めて、追い詰める。いつもなら、怒り出しそうな雪兎が今日は頬を上気させて、桃矢の気がすむようにさせていた。そうして、少しばかり後ろめたい言い訳は、心の中に閉じ込める。
『────だって、…ちょっと気持ちよかったんだもの。』
あの時の『吹雪』は恐ろしくなかった。自分の力を持て余し、大切なものを傷つけたことに『吹雪』自身が傷ついていた。すまない事をしたと詫びられ、そうして、あの冷たい手が火照った雪兎の肌を滑った時、思いがけずぞくりとした感覚が全身を走って、声をあげてしまった。
「喉が嗄れるまで、絶対勘弁してやらねえからな」
むきになった桃矢の乱暴な仕草に、揺さぶられる。
恥ずかしいほどに、声が濡れていた。
けれど、もう止めようもなく雪兎は腕を伸ばす。
「まだ────寒い。とーや────」

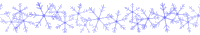

遠ざかる風の音を聞きながら、桃矢はようやく体を離して枕に沈んだ。雪兎が、おぼつかない視線で風の音を追う。
「900ヘクトパスカルの台風なみ低気圧ってところだったね」
「あいつの話なら、もうしたくねーぞ」
「違うよ。とーや、が。」
疲労の色が見える目元を笑わせて雪兎が答えると、桃矢は表情を改めて、そっと頬を撫でた。
「…ごめん。」
「うん」
「だけど、気圧も下がるさ…。
お前ときたら、あんな目にあったってのに、
あっという間にほだされちまうんだからな」
「そんなこと、ないよ」
控えめな雪兎の否定を無視して、桃矢は大げさにため息をついた。
「お前に拒否されたと思ってないぞ、あいつは。
また、お前にちょっかいだされちゃ、かなわねーな」
「薪がいくらあっても足りないねえ」
的外れなことを平気で言って笑った雪兎が、ふと声を潜めた。
「でも────ぼく、もう見分けがつくと思う。桃矢と…あの…」
「…」
それきり赤くなって、口をつぐむ。
桃矢は、温かい体を抱き寄せ、風の音を遮るようにぎゅっとダウンケットを引き上げた。
「ふたり」 了
(☆)2002年「封」
ごめんなさい。なんなの、これは…と、思いつつ。
1月2月は、桃矢君にいい思いをさせよう月間ということで(^^;)
雪兎さん、ごめんなさい〜〜〜;;;
TOP HOME